梅津時比古セレクション 1/ゴーシュを聴く(音楽書)
宮沢賢治研究
春秋社


4,400円(税込)
音楽文化をめぐる評論の新しい地平。『《セロ弾きのゴーシュ》の音楽論』(芸術選奨文部科学大臣賞)ほか。賢治研究の新たな視点。
- 収載内容
-
- 《セロ弾きのゴーシュ》の音楽論――音楽の近代主義を超えて
- プロローグ
- 第一章 楽器の思想
- 『第六交響曲』
- セロもずゐぶん悪いのでした
- ゴーシュの楽器
- 上達しなかった賢治
- 楽器を考察する視座
- 穴あきのセロ
- 子狸の指摘
- 弘法、筆を選ぶ
- 楽器を手段と見る二元性
- 表現の核としての楽器
- ビルスマの二つのバッハ
- 名器の思想
- 間身体性
- 演奏者と一体となる楽器
- ゴーシュが選んだセロ
- 第二章 テクニックの思想
- 三毛猫の訪問
- 『印度の虎狩』
- 三毛猫と『トロ(イ)メライ』
- 三毛猫と『春の祭典』
- 音楽と近代主義
- フルトヴェングラーにおける近代主義批判
- フルトヴェングラーとカラヤン
- 合理主義と商業主義の結び付き
- 金星音楽団の楽長はカラヤン型
- 音楽とテクニックの切り離し
- レオニード・クロイツァーの教育
- 三人のピアニスト
- テクニックとメカニズム
- 指の練習
- 指が届かない曲はない
- リストの演奏は難しくない?
- 身体が演奏し、身体が聴く
- 批判における身体性の欠如
- ゴーシュの練習法
- 音楽のダイナミズム
- 音楽記号学の視点
- 『春の祭典』の衝撃
- ベジャールの『春の祭典』
- 形而上学的転倒・倒置の過程
- ゴーシュが感動を与えた演奏
- 水を呑むゴーシュ
- 『春と修羅』
- ほとばしる修羅
- 崩壊する主体としての修羅
- 「修羅」としてのセロの演奏
- 第三章 音程の思想
- 「糸が合はない」
- 左手の価値観
- チューニング
- 演奏家の音程
- 調律法
- バッハの「福音(ふくいん)律」
- 近代主義と商業主義による平均律
- 調律の芸術
- 狂ったヴァイオリン・ソナタ
- かっこうの声
- 完全なる調和
- 鳥が飛ぶ
- エピローグ
- 註
- あとがきにかえて
- 参考文献(本文中及び註にあげたもの以外)
- インテルメッツォ
- 夢の道
- オペラシティの猫
- 《ゴーシュ》という名前 ――《セロ弾きのゴーシュ》論
- はじめに
- 第一章 ゴーシュとかっこう
- ゴーシュの名の響き
- 名前の由来の二説
- ゴーシュはフランス人か?
- ドイツ語の「かっこう」
- 現代の辞典に見る「かっこう」
- 賢治の独和辞典
- 「かっこう」の古語の登場
- ドイツにおける「かっこう」の盛衰
- ZYPRESSENなど賢治が用いた外国語
- ゴーシュ以外のゴーシュ
- 「ゴーシュ」が登場した時期
- ドイツ語への憧れ
- 最後まで所有していたドイツ語の本
- 第二章 『ヴィーナスの歌』の謎
- 不思議なドイツ語の本
- 賢治のドイツ語の読書
- アルノー・ホルツとは
- 徹底自然主義とは何か
- ホルツの秒刻体がもたらしたもの
- 秒刻体の文体の魅力
- 賢治における「秒刻体」
- カメラ・集音マイクの文体
- 擬音語・擬態語の多用
- 方言の導入
- デザイン的な字の組み方
- 日本におけるホルツの紹介
- ホルツに入ってゆく賢治
- 幻想と海底のイメージ
- 輪廻の思想
- 賢治の読書の特定
- 第三章 無知の知と性
- 銀河鉄道の夜
- 「銀河鉄道」という発想
- Gauchの登場
- そのほかの言葉
- 中世におけるGauchの位置
- 『ダフニス』の特色
- かっこうの詩
- 賢治と性
- 脱中心の思考
- 無知の知
- ゴーシュの方言
- ゴーシュと「かっこう」の紐帯
- おわりに
- 註
- 幻の声 あとがきにかえて
- 解説 三浦雅士
1 《セロ弾きのゴーシュ》の音楽論――音楽の近代主義を超えて
2 プロローグ
3 第一章 楽器の思想
4 『第六交響曲』
5 セロもずゐぶん悪いのでした
6 ゴーシュの楽器
7 上達しなかった賢治
8 楽器を考察する視座
9 穴あきのセロ
10 子狸の指摘
11 弘法、筆を選ぶ
12 楽器を手段と見る二元性
13 表現の核としての楽器
14 ビルスマの二つのバッハ
15 名器の思想
16 間身体性
17 演奏者と一体となる楽器
18 ゴーシュが選んだセロ
19 第二章 テクニックの思想
20 三毛猫の訪問
21 『印度の虎狩』
22 三毛猫と『トロ(イ)メライ』
23 三毛猫と『春の祭典』
24 音楽と近代主義
25 フルトヴェングラーにおける近代主義批判
26 フルトヴェングラーとカラヤン
27 合理主義と商業主義の結び付き
28 金星音楽団の楽長はカラヤン型
29 音楽とテクニックの切り離し
30 レオニード・クロイツァーの教育
31 三人のピアニスト
32 テクニックとメカニズム
33 指の練習
34 指が届かない曲はない
35 リストの演奏は難しくない?
36 身体が演奏し、身体が聴く
37 批判における身体性の欠如
38 ゴーシュの練習法
39 音楽のダイナミズム
40 音楽記号学の視点
41 『春の祭典』の衝撃
42 ベジャールの『春の祭典』
43 形而上学的転倒・倒置の過程
44 ゴーシュが感動を与えた演奏
45 水を呑むゴーシュ
46 『春と修羅』
47 ほとばしる修羅
48 崩壊する主体としての修羅
49 「修羅」としてのセロの演奏
50 第三章 音程の思想
51 「糸が合はない」
52 左手の価値観
53 チューニング
54 演奏家の音程
55 調律法
56 バッハの「福音(ふくいん)律」
57 近代主義と商業主義による平均律
58 調律の芸術
59 狂ったヴァイオリン・ソナタ
60 かっこうの声
61 完全なる調和
62 鳥が飛ぶ
63 エピローグ
64 註
65 あとがきにかえて
66 参考文献(本文中及び註にあげたもの以外)
67 インテルメッツォ
68 夢の道
69 オペラシティの猫
70 《ゴーシュ》という名前 ――《セロ弾きのゴーシュ》論
71 はじめに
72 第一章 ゴーシュとかっこう
73 ゴーシュの名の響き
74 名前の由来の二説
75 ゴーシュはフランス人か?
76 ドイツ語の「かっこう」
77 現代の辞典に見る「かっこう」
78 賢治の独和辞典
79 「かっこう」の古語の登場
80 ドイツにおける「かっこう」の盛衰
81 ZYPRESSENなど賢治が用いた外国語
82 ゴーシュ以外のゴーシュ
83 「ゴーシュ」が登場した時期
84 ドイツ語への憧れ
85 最後まで所有していたドイツ語の本
86 第二章 『ヴィーナスの歌』の謎
87 不思議なドイツ語の本
88 賢治のドイツ語の読書
89 アルノー・ホルツとは
90 徹底自然主義とは何か
91 ホルツの秒刻体がもたらしたもの
92 秒刻体の文体の魅力
93 賢治における「秒刻体」
94 カメラ・集音マイクの文体
95 擬音語・擬態語の多用
96 方言の導入
97 デザイン的な字の組み方
98 日本におけるホルツの紹介
99 ホルツに入ってゆく賢治
100 幻想と海底のイメージ
101 輪廻の思想
102 賢治の読書の特定
103 第三章 無知の知と性
104 銀河鉄道の夜
105 「銀河鉄道」という発想
106 Gauchの登場
107 そのほかの言葉
108 中世におけるGauchの位置
109 『ダフニス』の特色
110 かっこうの詩
111 賢治と性
112 脱中心の思考
113 無知の知
114 ゴーシュの方言
115 ゴーシュと「かっこう」の紐帯
116 おわりに
117 註
118 幻の声 あとがきにかえて
119 解説 三浦雅士
- 商品詳細
-
商品説明 当巻には近代主義をテーマとして尖鋭な二作品、芸術選奨文部大臣賞・岩手日報文学賞賢治賞に輝く『《セロ弾きのゴーシュ》の音楽論』と賢治研究のユニークな話題作『《ゴーシュ》という名前』を収録。解説は三浦雅士氏。
「重要なのは、ゴーシュが読者を音楽の新しい次元へと誘うのと同じように、賢治もまた読者を文学の新しい次元へと誘っているということなのである。賢治自身は夭折によって持続を断たれたが、生まれ変わってでも書き続けたいと思っていたに違いない。とすればつまり、梅津は二冊の賢治論によって、新しい音楽だけでなく、新しい文学の誕生をも待望していると述べているのだということになる。むろん、読者の多くも同じだろう。だが、いま現在世界に、ホルツや賢治に匹敵する情熱に突き動かされている詩人や小説家がどれだけいるだろうかと問うてみるがいい。......状況は厳しいが、しかし突き進むほかにないだろう。ここでも私は梅津に深く感謝したいと思う。こういう根源的な問い、根源的な決断に接する機会は、近来、いよいよ稀になってきていると言っていいからである。」(三浦雅士氏の解説より)商品番号 F0241144 ジャンル 書籍・辞典 サイズ 四六 ページ数 402 著者 梅津時比古 初版日 2025年09月20日 ISBNコード 9784393936184
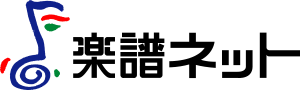
 2,200円以上で送料無料!
2,200円以上で送料無料!